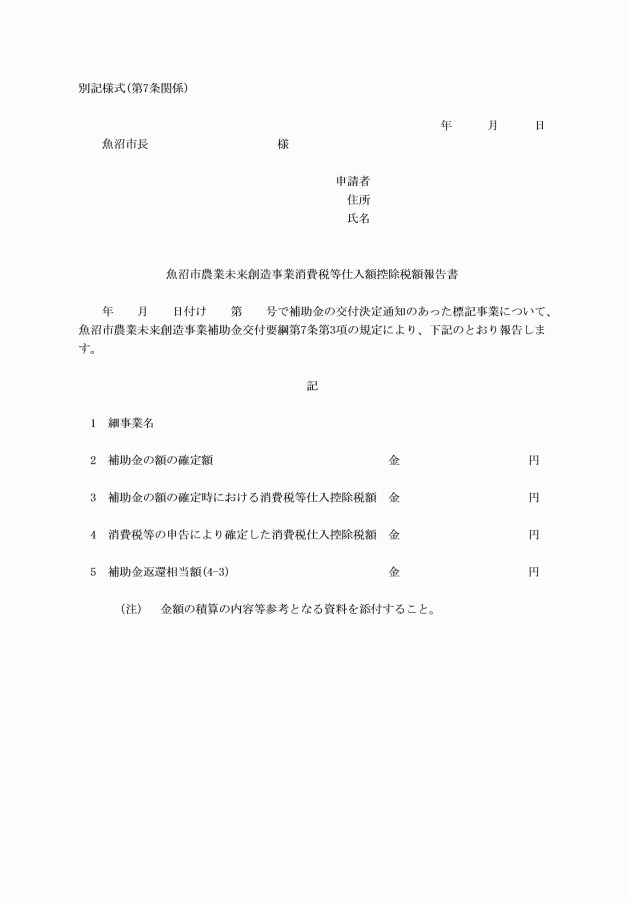○魚沼市農業未来創造事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第84号
(趣旨)
第1条 農業の将来にわたる持続性の確保及び耕作放棄地の増加抑制等による農村環境の維持を図り、魚沼市農業の未来創造に資するため、担い手の確保とその経営継続・発展等地域計画の実践に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付条件)
第3条 規則第6条第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。なお、この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときもまた同様とする。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営等を図らなければならないこと。
(4) この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(5) この補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(交付申請書)
第4条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(1) 魚沼市内に住所を有し、市税の滞納がないこと。
(2) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第3項の規定による地域計画において、将来の農業を担う者と位置づけられているか、位置づけられることが確実な者であること。
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、別表の補助の対象となる経費の欄に掲げる事業ごとに次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 経費の配分の変更 事業費の30パーセントを超える増減。ただし、補助金額に変更のない場合は除く。
(2) 事業の内容の変更 事業主体の変更、機械及び施設の新設及び廃止、施行箇所の変更又は機械若しくは施設の設計単位ごとの事業量の30パーセントを超える変更
(実績報告書)
第7条 規則第13条の報告は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の最終開庁日のいずれか早い時期までとする。ただし、市長が特に必要があり、かつ予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第8条 規則第6条第1項第3号により市長の指示を受けようとする場合は、事業が予定の期間内に完了しない又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、規則第16条に定めるもののほか、助成対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(財産処分の制限)
第10条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱(平成25年魚沼市告示第132号)
(2) 魚沼市担い手農業経営継続緊急支援事業費補助金交付要綱(平成26年魚沼市告示第130号)
(3) 魚沼市新規就農者援助事業補助金交付要綱(平成28年魚沼市告示第40号)
(4) 魚沼市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱(令和4年魚沼市告示第22号)
(5) 魚沼市農業応援元気づくり事業補助金交付要綱(令和5年魚沼市告示第39号)
(6) 魚沼市スマート農業推進事業補助金交付要綱(令和5年魚沼市告示第40号)
(7) 魚沼市外国人農業人材受入助成金交付要綱(令和5年魚沼市告示第121号)
(魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の魚沼市農業者育成支援事業費補助金交付要綱(以下、この項において「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第5条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
(魚沼市新規就農者援助事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
4 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の魚沼市新規就農者援助事業補助金交付要綱(以下、この項において「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第4条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
(魚沼市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
5 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の魚沼市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱(以下、この項において「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第4条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
(魚沼市農業応援元気づくり事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
6 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の魚沼市農業応援元気づくり事業補助金交付要綱(以下、この項において「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第4条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
(魚沼市スマート農業推進事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
7 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の魚沼市スマート農業推進事業補助金交付要綱(以下、この項において「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第7条、第11条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。
(魚沼市外国人農業人材受入助成金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
8 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の魚沼市外国人農業人材受入助成金交付要綱(以下、この項において「旧要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた者については、旧要綱第9条、第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条、第5条、第6条関係)
営農継続支援対策
種目 | 細目 | 補助の対象となる経費 | 補助率等 | 事業主体 | 摘要 |
農業用機械施設導入支援対策 | 国県助成発展支援 | 1 国県助成発展支援事業 国県の補助事業(市を経由して間接的に補助する事業に限る。)の採択が見込まれる設備・機械の整備に係る経費 | 当該補助金等の財源の一部として市以外から交付される額を除いた補助対象経費の10%以内。(ただし、認定新規就農者においては30%以内) 施設上限300万円 機械上限100万円 | 当該国県補助事業の事業主体となる者。ただし、リース会社が事業主体の場合は、要綱第5条第1号及び第3号の規定は適用しない。 | リース会社が事業主体の場合、機械施設等を借り受けて利用する農業者が要綱第5条各号の規定を満たす者であること。 |
市単独助成支援 | 1 農業用機械設備導入事業 農業用機械設備(農業用途以外に供されるような汎用性の高いものは除く。)の購入に係る経費で、次に掲げる要件を満たすもの (1) 国県及び市の補助対象となっていないこと。 (2) 同一年度内における同一の補助申請者の申請は1回までとし、1機種1台又は1棟のみとする。ただし、トラクター購入の際のアタッチメントについては、2種類までは補助対象とする。 (3) 1回の購入価格が、50万円以上(消費税及び付属品を含まない本体価格)の農業用機械であること。 | 補助対象経費の2/10以内で200万円を上限とする。(事業主体が、魚沼市優良モデル農業経営体に認定されている場合は対象経費の2.5/10以内で250万円を上限とする。) | 今後も地域農業の担い手として経営面積の拡大を図る者又は当該集落等において不耕作地の拡大等を抑制するため、自らの耕地を維持しつつ、不耕作地の懸念がある農地の耕作等を行う意向を示す者で、次のいずれかに該当する者 (1) 申請時における農地の経営面積が5ha以上の者又は事業実施後3年以内に経営面積が5haを超えることが確実な者 (2) (1)以外の小規模経営者等が2者以上で導入機械を共同利用する組織 (3) 中山間地域等直接支払制度の集落協定組織(この場合において、要綱第5条第3号の規定は適用しない。) (4) その他市長が認める者 | 事業主体の欄の(2)の者については、以下の要件を満たすこと。 (1) 導入機械等に係る経費の負担割合、利用方法、管理方法等からみて共同利用機械であることが分かる書類を交付申請書に添付すること。 (2) 当該集落等において不耕作地となる懸念がある農地について、導入機械等の耐用年数の範囲において積極的に耕作等を検討する旨の意向書を交付申請書に添付すること。 | |
2 農業用パイプハウス導入事業 農業用パイプハウス資材(遮光資材、潅水設備等及び50万円未満の付属品を含む。ただし、取付設置費用等は除く。)の購入に係る費用で、前項各号の要件に該当するもの。ただし、補助対象とする農業用パイプハウス資材、遮光資材、潅水設備等は新品に限るものとする。 | |||||
農業用機械施設導入支援対策 | 市単独助成支援 | 1 園芸・果樹用機械設備導入事業 園芸・果樹等の収益向上につながるものと認められる機械・器具の1件の購入経費(農業以外の用途にも供されるような汎用性の高いものは除き、税抜きで10万円以上のものに限る。) | 補助対象経費の1/2以内で50万円を上限とする。 (複数作目を対象とする事業主体欄の(1)の者にあっては、作目ごとにこれを適用する。また、助成は1申請者1作目につき年1回とする。) | 次のいずれかの者 (1) 特定の作目の生産・振興を図るための農業者等で組織する団体 (2) 新たに園芸作目の生産・出荷・販売に取り組む者。なお、既に園芸作物の生産等を行っている者であっても、新たな作目を対象として取り組む場合は対象とする。 | 事業主体の欄の(2)の者は、試作等を除き新たな園芸作目の生産出荷を開始する者であって、以下の要件を全て満たす者。 (1) 新たに生産・販売を開始する作目の販売額合計が3年後に概ね100万円を超えることを目標としていること。 (2) ほ場整備後のほ場での栽培又は栽培作目が地域園芸振興プランの推進品目又は水田収益力強化ビジョンの対象品目であること。 |
2 農業用業務車両等導入事業 農業用の通作又は業務車両の購入経費であって、農業法人等が新たな雇用者の労働環境整備及び新たな雇用者を活用した業務・販売拡大のために購入するもの | 補助対象経費の2/3以内で50万円を上限とする。 | UIJターン新規雇用支援事業の補助金を受けている者 | 補助対象とする農業用業務車両は、4ナンバーのキャブバンタイプ又は軽トラックに限るものとする。 | ||
3 スマート農業機器導入事業 次のいずれかの導入機器に係る経費 (1) 高精度位置情報技術等導入事業 農業機械の自動操舵導入に係る経費 (2) 農業用ドローン導入事業 主に農薬の散布を目的とした農業用ドローンの導入に係る経費 (3) 省力化及び効率化のための機械設備導入事業 ラジコン草刈機、園芸作物の自動収穫ロボット等導入に係る経費 (4) 先進技術活用環境制御機械設備導入事業 AIを用いた水田管理システム、ハウス温度等の環境管理システムの導入に係る経費 | 補助対象経費の2/3以内((2)の事業は1/2以内)で600万円を上限とする。 | 次のいずれかの要件を満たす者 (1) 農地所有適格法人であって経営面積を20ha以上保有し、50歳未満の者が従業員を含めて2名以上いること。 (2) 3者以上で構成された団体で次の要件を全て満たす者。 ア 代表者の定めがあること。 イ 構成員のうち50歳未満の者が2/3以上を占めること。 ウ 構成員全員が本事業の交付対象となっている他の団体に属していないこと。 | (1) 事業の採択に当たっては、次の要件を全て満たすこと。 ア 補助対象とする機械施設等は新品のもの又は新設、新築によるものとする。 イ 上記機械施設等は、原則として耐用年数5年以上のものとする。 ウ 当該導入機械設備、技術等を活用した作業受託による受託面積の拡大について、あらかじめ市の承認を受けること。 エ 過去に本事業の補助金を受けた者にあっては、前回の補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後1年を経過していること。 (2) 事業の実施に当たっては、市が必要に応じて行う実地調査に協力するとともに、成果報告会等へ出席すること。 (3) 事業の完了後は、次に掲げる報告等を行うこと。 ア 補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、魚沼市農業未来創造事業実施要領(令和7年魚沼市訓令第14号。以下「要領」という。)に規定する実績書により、計画の達成状況を報告すること。 イ アによる報告の最終年度において、計画に対する達成率が70%未満の場合は、改善計画を作成し、翌年度の6月末日までに市長に提出するとともに、達成状況の報告を5年間延長する。 ウ イによる5年後の報告においてもなお達成率が70%の場合は、再度改善計画を作成するとともに、報告期間をさらに5年間延長する。 エ イ及びウの場合において、目標達成率が70%未満となった理由が、天災その他事業主体の責めに帰すべきでないものの場合は、報告期間を延長しない。 | ||
営農活動支援対策 | 営農規模拡大支援 | 1 受託地代助成事業 受託水田10a当たりの賃借料が、物納の場合は15kg以上、賃料の場合は4,500円以上である賃借水田の賃借料 | 対象となる賃貸借水田10a当たり1,500円 (事業主体が、魚沼市優良モデル農業経営体の場合にあっては、10a当たり2,000円。ただし、親が所有する水田を除く。) | 魚沼市再生協議会が実施する魚沼市独自支援制度に全加入しており、次のいずれかの要件を満たす者 (1) 賃貸借水田を含み経営面積が5ha以上ある者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実なこと。 (2) 賃貸借による水田を2.5ha以上有する者でその期間が3年以上あるか又は3年未満であっても契約満了後5年以上の契約更新が確実であること。 | (1) 交付対象となる賃貸借契約の確認基準日は、事業実施年度の6月1日とする。 (2) 交付対象となる受託水田の面積は農地台帳により確認することを原則とするが、現況面積が著しく乖離しており、申請者の申し出により市長が適正と認めるときは水田台帳面積に置き換えることができる。 (3) 農地中間管理機構を通じた貸借で、ほ場整備事業実施地区の場合、換地終了までの使用貸借契約期間については、申請者からの支払実績の写し等の提出を受けて賃借料の確認を行うことができるものとする。 |
2 遠距離通作水田受託支援事業 主要作業所等から7km以上離れた魚沼市内の受託水田の耕作に係る掛かり増し経費。ただし、適正な農産物生産又は適正管理が行われている水田であること。 | 対象となる賃貸借水田10a当たり1,000円(ただし、親が所有する水田を除く。) | (1) 交付対象となる賃貸借契約の確認基準日は、事業実施年度の6月1日とする。 (2) 主要作業所は事業主体ごとに市内の1作業所を登録すること。 (3) 距離計測は、登録した主要作業所から申請された支援対象水田(面的なまとまりのある水田の場合はその中心)までの距離を、国県道及び主要市道を経由する場合の距離として魚沼市地理情報システムにより計測する。 | |||
3 狭小水田受託支援事業 受託している狭小水田の耕作に係る掛かり増し経費で次の要件を満たすもの (1) 当該水田1筆の農地台帳面積が7a以下であるもの。ただし、畔抜き等で現況地積が7aを超えている場合は対象としない。 (2) 当該水田において適正な農産物生産又は適正管理が行われていること。 | 対象となる賃貸借水田10a当たり1,000円(ただし、親が所有する水田を除く。) | (1) 交付対象となる賃貸借契約の確認基準日は、事業実施年度の6月1日とする。 (2) 対象水田の面積確認は、農地台帳によるほか、必要により航空写真での確認や現地調査を実施する。 | |||
4 水稲中間管理再委託支援事業 受託農家が受託農地の地権者等に対し、稲作の中間管理作業(草刈、水管理、防除又は施肥に限る。)を委託する場合の経費 | 契約1件当たりの経費の1/3以内とし、上限3万円とする。ただし、1事業主体当たり補助の対象となる契約は、1年につき5件を上限とする。 | 前項までに規定する事業主体要件に該当する農業者で、受託農地について、地権者等に中間管理の再委託契約を行っている者 | 再委託契約は、再委託する中間管理の業務内容、対象ほ場、委託金額、期間について書面により行うこと。 | ||
5 担い手支援・地域総応援団設立活動支援事業 集落等の合意のもと担い手の営農活動を支援して環境保全を図っていくことを目的にした団体(担い手地域総応援団)の活動経費及び担い手応援・環境保全のために共同活動に使用する草刈機の導入に要する経費。ただし、団体の活動経費は次に掲げるものを除く。 (1) 団体の運営に係る経常的な経費(家賃、電気料、電話料、自動車の維持費用(燃料・オイル・車検費用・保険料)及びその他類似の性格を持つ経費をいう) (2) 事務作業に係る人件費 (3) 飲食費(会議等の湯茶は除く。) (4) 他の目的に転用できる備品等の購入 (5) 作業委託等の外注費 (6) 租税公課 (7) 他の補助事業等と重複する経費 (8) その他市長が不適当と認めたもの | (1) 団体の活動経費に対して年間10万円を上限とする。ただし、補助対象経費が10万円未満の場合は、その額を上限とする。 (2) 草刈機導入経費に対して ア 自走式の場合 経費の4/10以内で12万円を上限とする。 イ 着脱式の場合 経費の1/3以内で100万円を上限とする。 | 地域計画の推進を通じて集落・地域の課題解決の取組を行う担い手地域総応援団として、次の要件を全て満たす団体 (1) 市内に住所又は本拠地を有する農業者を含む5名以上で構成されていること。 (2) 集落等により承認を受けていること。 (3) 代表者の定めがあること。 (4) 運営規約があること。 (5) 構成員が他地区において本事業の補助対象団体に属していないこと。 (6) 担い手地域総応援団として市長が認めた団体であること。 | (1) 事業実施計画書に、集落、農家組合、その他活動組織の合意により設立された旨が分かる書類(議事録又は合意した組織の長が証明する資料等)を添付すること。 (2) 事業実施初年度に担い手地域総応援団登録申請をすること。なお、登録内容に変更があった場合も同様とする。 | ||
外国人就労支援 | 1 外国人農業人材受入支援事業 基準日(令和7年4月1日)以降において、外国人農業人材(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に規定する一般監理事業又は特定監理事業を行う監理団体と契約等を締結し、認可法人外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者と雇用契約を締結し、農業分野(耕種農業全般・畜産農業全般)に従事する者をいう。)を受け入れ、又は基準日以降に外国人農業人材を受け入れる場合において、これに伴う渡航費用(往路)等・取次費用、健康診断費用、渡航前及び入国後講習等費用、外国人労働者保険等その他受入れ及び講習等に要する費用 | 補助対象経費の2/3以内で受け入れる外国人農業人材1人当たり上限15万円(基準日において受け入れている又は基準日以降において受け入れた外国人農業人材1名につき1回限りとし、1事業者につき単年度5名を上限とする。) | 基準日において外国人農業人材を雇用している又は基準日以降に外国人人材を雇用している農業者 | (1) 基準日又は基準日以降に外国人農業人材を受け入れた日の翌日から2月以内に市長に申請すること。 (2) 補助率等の欄の「外国人農業人材1名につき1回限り」は、受入先の変更等があっても同様に通算して1回限りとする。 | |
営農活動向上支援 | 1 スマート農業技術導入事業 次のいずれかの技術導入に係る経費 (1) 先進技術活用農産物生産等導入事業 リモートセンシング撮影、画像評価・分析並びに土壌分析に係る経費 (2) 農業用ドローン技術認定取得事業 農作業に係るドローン技術及び安全な飛行に関する知識を取得するために受講する講習等に係る経費 | 補助対象経費の2/3以内で200万円を上限とする。 | 次のいずれかの要件を満たす者 (1) 農業法人であって経営面積を20ha以上保有し、50歳未満の者が従業員を含めて2名以上いること。 (2) 3者以上で構成された団体で次の要件を全て満たすもの ア 代表者の定めがあること。 イ 構成員のうち50歳未満の者が2/3以上を占めること。 ウ 構成員全員が本事業の交付対象となっている他の団体に属していないこと。 | 当該技術等を活用した作業受託による受託面積の拡大の承認を受けること。 | |
組織体等向上対策 | 研修の場設置・参加支援 | 1 研修の場設置・参加支援事業 当該法人で行う経営発展のための技術研修の実施、講師手配や視察等の実施に要する旅費及び謝金等の経費 | 補助対象経費の1/2以内で10万円を上限とする。ただし、1法人につき年1回に限る。 | 市内に活動拠点を置く農業法人 | 視察の対象経費は、旅費及び謝金等に限る。 |
組織化・会社化支援 | 1 組織化・会社化支援事業 (1) 3戸以上の農業者(以下「3戸以上農業者」という。)が農地所有適格法人を設立するための以下の経費 ア 法人化のための研修等に参加する経費 イ 定款認証及び登記費用 ウ 司法書士等による代行費用 (2) 農業者が経営の効率化・安定化を目的に農地所有適格法人を設立するための前号アからウまでに掲げる経費 | (1) 3戸以上農業者の場合 補助対象経費の1/2以内で50万円を上限とする。 (2) それ以外の場合 補助対象経費の1/2以内で30万円を上限とする。 | (1) 3戸以上農業者の場合 3戸以上農業者で組織された法人化を志向する団体 (2) それ以外の場合 個人農家で法人化を志向する者 | 法人設立のための研修等経費は、法人設立及び設立後の運営に関する研修等に係る経費とし、視察の対象経費は、旅費及び謝金等に限る。 |
別表第2(第2条、第5条、第6条関係)
新規就農支援対策
種目 | 細目 | 補助の対象となる経費 | 補助率等 | 事業主体 | 摘要 |
新規就農者支援対策 | 新規就農支援 | 1 新規就農者支援事業 本市に住所を有し、市内の農地を新たに取得し若しくは借り上げ又は所有して、意欲を持って新たに農業を始める者及び農家子弟等(本市に住所を有し、親又は親が経営する法人で就農しているか雇用されて就農している50歳未満の者であって、次世代に経営継承を受ける見込みの者をいう。以下同じ。)に係る次の経費を補助するもの (1) 営農支援 就農に当たっての施設・機械の整備、肥料代、種子代等の営農に係る経費 (2) 技術習得支援 新規就農者が農業大学校及び指導農業士や農業法人の下で実習するための受講料、旅費、宿泊費等の経費 (3) 家賃支援 住宅1月当たりの家賃 | (1) 営農支援の場合 補助対象経費の10/10以内で30万円(実績が30万円以下の場合はその金額)を上限とし、補助の期間は最長で5年間とする。 (2) 技術習得支援の場合 補助対象経費の1/2以内で15万円を上限とし、補助の期間は最長で2年間とする。 (3) 家賃支援の場合 補助対象経費の10/10以内で対象となる住宅の区分ごとに次に掲げる金額(実績が上限額以下の場合はその金額)を上限とし、補助の期間は最長で5年間とする。 ア 空き家 月額5万円、 イ 公営住宅等 月額2万円 ウ 民間賃貸住宅 月額5万円 | 新規就農から3年以内の者で、事業区分ごとに次の要件に該当する者 (1) 営農支援の場合 次のいずれかに該当する者 ア 年齢50歳未満であって経営開始資金の受給者 イ ア以外の者で、年齢50歳未満の者であって30a以上の農地を自ら耕作する者 (2) 技術習得支援の場合 前号ア又はイに該当する者のほか、農家子弟等 (3) 家賃支援の場合 新規就農者のうち公営住宅等を借り上げたUIJターン者。ただし、魚沼市定住促進事業の規定による補助金の交付を受けている者は除く。 | 事業主体の欄(1)アの経営開始資金の受給者とは新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農陳水産事務次官依命通知)に掲げる経営開始資金を受給している者をいう。 |
2 定年帰農者等支援事業 農業従事に必要な資材、装備等の取得その他就農準備に要する経費 | 補助対象経費の10/10以内で20万円を上限とする。ただし、申請は1回限りとする。 | 他産業を退職後3年以内に新たに又は本格的に農業を開始しようとする者であって、次の要件に該当する者 (1) 申請時点において50歳から65歳までの者 (2) 就農後、農業を3年以上継続する見込みである者 | 事業主体の欄の「本格的に農業を開始」とは、年間60日以上の期間を農業に従事することをいう。 | ||
3 UIJターン新規雇用支援事業 次の各号に掲げる者(以下「UIJターン者」という。)を正規雇用した農業法人等の、当該雇用に要する経費 (1) 当市の出身者で、転出後、市外に1年以上居住し、申請時点において当市に住民登録している者 (2) 当市以外の出身者で、出身地以外(当市を除く)に居住した後、申請時点において魚沼市に住民登録している者 (3) 当市以外の出身者で、申請時点において魚沼市に住民登録している者 | 正規雇用者1人につき月額3万円を3年間助成する。ただし、雇用月数が1月に満たない場合は日割計算とし、千円未満は切捨てとする。 | 市内に本社を有する新たにUIJターン者を雇用した農業法人又は法人化を目指す農業者 | (1) UIJターン者は令和7年2月1日以降に本市に住民登録をした者とする。 (2) 正規雇用は、令和7年4月1日以降に雇用期間の定めのない労働契約に基づき農業法人が雇用することをいう。 (3) 農閑期等に他の産業に従事する期間については、経費補助の対象としない。 (4) 助成の対象となるUIJターン者1人につき3年間(助成初年目が12月に満たなくとも1年間とし、以後連続した2年間)に限り助成するものとする。ただし、雇用先を変更する場合も期間は通算するものとする。 |
別表第3(第2条、第5条、第6条関係)
農村集落維持支援対策
種目 | 細目 | 補助の対象となる経費 | 補助率等 | 事業主体 | 摘要 |
農村集落維持支援対策 | 高付加価値作物等試作生産支援 | 1 高付加価値作物等生産・販売支援事業 水稲耕作条件が不利な山間地又は付加価値の高い農産物生産の取組に意欲的な地域において高付加価値農産物(米を含む。)の試作又は生産・販売等に要する以下の経費。ただし、機械等の購入に要する経費を除く。 (1) 品目等研修・検討経費 (2) 試作経費 (3) 生産・出荷及び販売体制の整備に要する経費 | 補助対象経費の2/3以内で100万円を上限とし、補助の期間は連続する2年間までとする。 | 次のいずれかに該当する者 (1) 市内の山間地等の集落若しくは農家組合又は農業者を含む3名以上で組織された団体 (2) 山間地等のほ場を受託しており、そのほ場を活用し高付加価値作物等の生産に意欲を持つ者 (3) その他の農業者等で市長が特に認める者 | (1) 補助の対象となる経費の欄に掲げる「水稲耕作条件が不利な山間地」とは、受益地の過半が次のいずれかに該当する地域をいう。 ア 振興山村又は特定農山村の指定地域 イ 中山間地域等直接支払制度の実施地域 (2) 同欄の「付加価値の高い農産物生産の取組に意欲的な地域」とは、高付加価値農産物等((1)以外の地域にあっては園芸品目に限る。)の生産出荷計画等の熟度が高いと市長が認める地域をいう。 |